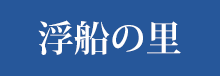来ーたーよー!
9月なのに、とんでもなく暑い小高です。
やってきました。
起きて4齢の、お蚕さま5,000頭。

あ。
今年の夏は本当に暑かったけど、久米さんは元気です!
道中のおしゃべり尽きず田村市都路まで蚕を引き取りに行き、浮船の特設ベッドにチェックインしてもらいました。

手前の直立の蚕さんは、寝ている状態。
食べやすいように細かく刻んだ桑の葉と5,000頭の蚕がひとつに丸まって移動してきたので、ふんわりかつダイナミックにかたまりをほぐしましたが、起きない。
一方で起きている蚕さんは、すでに周りの桑を食べ始めています。

中央右めの方はやる気満々の様子で、桑をハミハミしています。
こうして、卵からかえった瞬間からそれぞれの蚕生を歩みはじめ、繭になるタイミングも少しずつ違うのだな、と実感します。
桑畑をお借りしている佐藤さんご夫妻に、「よろしくお願いします」の挨拶に行きました。
働き者のおかあさん、今日も元気に鍬をふるっていました。
歯医者から帰ってきたおとうさんにも会うことが出来、いよいよ2023年の秋繭がスタートです。
わたしはいったん、ここで帰宅。
来週、蚕たちが5齢を迎えて食欲が最盛期になったころに、戻る予定です。
お菓子の小枝くらいの蚕ちゃん、どのくらい成長してるかなー!
日中、もう少し涼しくなっていますように。
(裕)
育つ速さ
9/5に浮船の里に来たお蚕様も、9/9に4齢の眠りに入りいよいよ繭づくり前の最後の週になりました。

4齢の眠りに入るお蚕様。まるで手を合わせているように見えます。
てっきり晩秋蚕かと思っていたのですが、飼育標準表こと養蚕カレンダーによると・・・
なんと初秋蚕の飼育日数と合致しているため、思ったより早く(と言っても1日2日早いだけなのですが)9/18に上蔟の予定となりました。
今年の夏は長雨の続く異常気象で日照不足による被害を心配していましたが、桑の木には特別な被害もなく、青々としたきれいな葉っぱを繁らせてくれました。

光り輝く桑の新芽には赤味がさしていて、とても柔らかい。
桑の枝を切りに行くときは、重装備で畑に入ります。畑には色々な虫がいますし、人の背丈ほどに大きくなった桑の、樹液や葉っぱにかぶれることもあるので気をつけます。

切り口から流れ出す樹液。

久米さん(155㎝)の背を越す桑の枝。
浮船の里での養蚕は本当にほんの少しの飼育頭数ですが、養蚕を通していろいろなことを知ったり感じたり、かけがえのない体験をしていると思います。
便利さの代わりになくしたもの・こと。
先人の残した道しるべがほんとうになくなってしまわないように、小さな規模でも活動し続けていきたいです。
MIMORONE
前回訪れたのが6月だったから、
また季節の変わり目に小高に来たことになる。
青空がどこまでも広がる文句なしの青空で、
私はほっとしていた。
何しろ、私が小高に行くと
半端じゃない雨が降ることが多かったからだ。
今回ばかりは、雨だけは避けたかった。
10月15日、16日は小高の秋祭り。夫婦で参加させていただいた。
私にとってもそうだけれど、
それ以上に浮船の里の皆さんにとっても、
とても大切な秋祭りだったんじゃないかと思う。
小高に新しいことばがひとつ生まれた。
浮船の里の絹糸から作る製品ブランド「MIMORONE」
これが秋祭りでお披露目になった。
小高で育てたお蚕様の糸を小高の草木で染め上げて作った、
100%小高のブランドだ。

草木の繊細な色と、シルクの優しい手触り。
アクセサリーは秋祭りに来たみなさんを惹き付けて、
飛ぶように売れていった。
売れるのは楽しい。
このアクセサリーがどんどんいろんな人のところに行くのだから。
その先々を想像して、また楽しくなる。
少しずつ、世の中に「MIMORONE」の色が広がっていく。

「みもろ」とは大和ことばで「神様が見守る場所」の意味だそうだ。
小高の豊かな自然、糸を生み出すお蚕様、そして浮船の里の人たち。
きっと、神様が見守っている。
「ね」は「音」である。
音色ということばがあるように、色とりどりの糸のイメージと、
浮船の里に聞こえる独特の音たちをイメージした。
機織りの音、お蚕様の桑を食む音……。
確かに、この場所は色と音に溢れている。
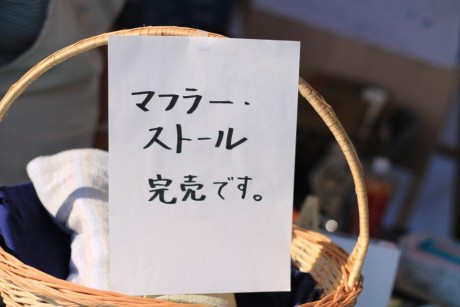
MIMORONEの色が、小高から、みんなを幸せにする。
私たち夫婦もいつか、そんなものを作りたい。
そんな話を日に焼けた帰り道、話していたのでした。
参加させていただき、ありがとうございました。
(木田修作)
小高天織
2015年シルバーウィーク、久しぶりに訪れた浮船の里では、縦糸にも横糸にも小高で育てたお蚕様の繭から取った正真正銘小高産の糸を使い、京都からはるばる届いた明治時代の織り機によって、ついに小高天織が織られ始めていました。
– * –
明治時代の織り機はバラバラの状態で浮船の里に届いたのですが、織姫が「博物館等で見た織り機はこんな感じだったはず!」と想像しながら組み立てたそうです。
– * –
下の写真、この三色の帯が小高天織の印になる予定で、この色は小高を象徴しています。
赤は紅梅の里。緑は懸の森。青は群青。
– * –
小高天織を織っている様子を短いムービーにしてみましたのでご覧ください。
(く)
学生ボランティアさん達と桑の剪定
去る3月28日から29日に、今年のお蚕様のための蚕部屋の増築と桑の剪定をしました。
今年は浮船の里のメンバーと協力してくださる方の人数が少し心細いところに、大学生ボランティアさんが2泊3日で駆けつけて下さいました。 「はぴばす☆ふくしま」という、若者の力を必要な所に届ける活動をされている下枝さんが、大学生を8人も連れてきて下さいました。
「はぴばす☆ふくしま」という、若者の力を必要な所に届ける活動をされている下枝さんが、大学生を8人も連れてきて下さいました。 初日は蚕部屋の増築や、掃除やスペースの確保も協力して取り組んで頂き、早く予定をこなすことが出来ました。やはり若い力はとても頼もしいです。
初日は蚕部屋の増築や、掃除やスペースの確保も協力して取り組んで頂き、早く予定をこなすことが出来ました。やはり若い力はとても頼もしいです。
二日目はお借りしている桑畑で剪定のお手伝いをしていただきまして、予定よりもかなり早くに終わらせることが出来ました。すごいです。

お昼ご飯をみんなで一緒に食べた後、活動の振り返りの場でそれぞれが自分の感じた事や分かった事などを発表してくださいました。
「ここに来ないとわからないこと」「来て、自分の目で見て、話して、本当にどことも変わらないこと」「これからの自分の見つめる方向」など、小高で何かを感じていただけたようでした。
この体験が大学生たちにとって何かの良いきっかけに繋がれば嬉しいと思っています。
「はぴばす☆ふくしま」で参加してくださった皆様、本当にありがとうございました。