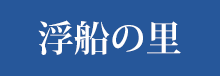年の瀬感
無事に上蔟が終わると、わたしたちの生活も通常運転に戻ります。
朝、お寝坊ができる!(といっても、早起きがなくなりいつもの起床時間に戻るだけ)と喜びたいところですが、小高に来たら、この時期だけの楽しみを見逃すわけにはいきません。
海から昇る朝日をみること。
浮船の里の蚕小屋から車で3分ほどの村上海岸は、だいすきな日の出スポットです。
昨日はあいにく焼けなかったので、今日に期待していました。
5時33分。

じんわりと、紅から青に変わっていく空。
ゆっくりと太陽が顔を出し、空が明るさを増します。
一定のリズムを刻む波に合わせて、自然と呼吸が整う感じ。
満足して海を後にしました。
昨日、蚕ベッドから個室マンションにお引っ越しした蚕たち。
つつがなく入居が終わったでしょうか。

まだうろうろとお部屋を探している子はいますが、とりあえず入居一歩手前までは来たようです。
カンボジア方式の桑の葉ベッドでも、着々と営繭が進んでいる様子に一安心。

あとは繭づくりに専念してね。
養蚕の道具もろもろをかたづけながら、「あぁ、今年も終わったな」と思いました。
まだ9月なのですが、秋繭が終わると確実に年の瀬感が襲来します。
そんな話を久米さんにしたら「ほんと、そんな感じ。もう今年は終わったね!」と達成感に満ちた(疲労感も少々)顔で同意してくれました。
桑の運搬に大活躍してくれた浮船号(軽バン)をきれいに掃除し、桑畑をお借りしている佐藤さんご夫妻に上蔟の報告に行き、最後のおしごと「繭かき」の日程を相談して帰ってきました。
そうそう、ひょこっと覗いた桑畑で、昨日までに捨てた桑の枝のなかから、健気に野生で生きていこうと頑張っていた蚕さんを1頭見つけました。

ごめんねぇ。。
心からお詫びして、桑の葉に乗って浮船に帰還してもらいました(この蚕さん、帰る道中で糸を吐き始めました)。
いまは蚕小屋に2種類の音がします。
ショワショワショワショワショワショワ
蚕が糸を紡ぐ音。
サワサワサワサワサワサワ
まだ食べたい蚕たちが桑を食む音。
2,3日もすればサワサワはショワショワに変わるでしょう。
この秋は、いくつの繭がとれるかしら。
おしまいに、ブログで載せきれなかった写真たちをここで大放出しようと思います。
2022年の秋繭の思い出に。






(ゆ)
カンボジアと空の旅
曇天からパラパラと雨の落ちてきた水曜日の始まり、蚕小屋に行くと昨晩あげた桑の葉がところどころ、こんもりと山になっていました。
そしてその陰で、ひっそりと糸を吐くお蚕さまの姿。

早い子の、繭づくりが始まりました。
探してみると、ちらほらと営繭に入った蚕の姿。
繭づくりのためのマンション・蔟(まぶし)を組み立てて、上蔟の準備にかかります。

体の色が飴色に変わり、営繭の準備万端な蚕さん。
一方で、まだまだ食欲旺盛に桑を食む蚕も多く、その体はうす青っぽくぷりっぷり。

なかには、蚕ベッドを抜け出して脱走を試みる、勇敢な冒険者もいます。

こらこら、戻りなさいね。君の居場所はそこじゃない。
営繭をはじめた蚕は全体の1割程度、予備軍が4割くらいと判断し、まだ食べる子用の桑刈に出かけます。
いつしか雨は上がり、小高らしいきれいな青空が広がっていました。

佐藤さんご夫妻が丁寧に手入れをしてくださった秋の桑は本当に健康優良児で、久米さんの背丈をゆうに超えるほどの成長ぶり。
この秋よく行き会った野生の蚕・クワコは、浮船の里の蚕たちより一足先に、繭になっていました。黄色い小さな繭、とてもかわいい。

桑刈と蚕小屋の掃除をしているたった1時間足らずの間にも、お知らせの来た蚕たちはどんどん前に進みます。
からだの中から不浄なものをすべて出して繭づくりを始める蚕のおしりから、見慣れぬ色の半固体の液体が出ていたので、ティッシュで拭ってみました。

おしっこと、最後に食べた桑かしら。
うーーーーんと細かくかみ砕かれています。
この状態のうんちは初めて見ました。
ほらほら、早い子はもううっすらと、わたしたちの目が届かない世界を作り上げようとしています。

上蔟は午後2時から本格的に行うことになり、腹ごしらえのランチへ繰り出しました。

今日までの期間限定スパイスカレー屋さん。
よし、これで上蔟に臨めるぞ。
はじめに、ぷりっぷりから峠を過ぎ、ちょっと縮んだ蚕たちを1頭残らず拾う作業です。
おお、壁の時計は宣言通りの午後2時ぴったりを指している!

ここから先は怒涛の作業で写真を撮る余裕もなく、すべての蚕の身の振り方が決まり大かたの片付けを終えたころには、夕方になっていました。
あぁ、広い空に浮かぶ雲の、なんと自由なこと。

明日の朝には蔟をすべて天井から吊り、蚕たちは空の旅に出発します。
第一陣より少し遅れて旅を始める子たちは、桑の枝をタワーにした「カンボジア方式」の場所で繭になってもらうことになりました。

ただいま午後9時半。
ブログを書きながら、すでに半分目が閉じそうです。
今日が無事に終わって、とにかくよかった。
あすの(蚕たちの)フライトに備えて、バタンキュー。。。(ゆ)
お蚕さまの力
2週目の小高にやってきました。

強力な助っ人が先乗りで浮船の里に来ていることを知っているので、今日は日立の海に寄り道しました。燃えるような朝焼けはなかったけれど、たくさんのカモメが羽ばたいているのような雲を従えて、日が昇りました。
とことこと、のんびり小高に到着。
さっそく蚕小屋の引き戸を開けると。。
むわっと迫る熱気と、桑の青い香り。

むちむち。
ぷりぷり。
そして独特のしっとりした質感。
1週間経ったお蚕さまの成長ぶりは、何年やっていても目を見張るものがあります。
件の強力な強力な助っ人というのは、小田原からやってきた梅農家の川久保和美さん、朝見さんご夫妻、佐藤宏子さんの4人。
川久保さんは、ことし5月、久米さんが弾丸で小田原にやってきたときの〝訪ねたい方リスト〟のひとり。震災後すぐに交流が始まり、久米さんは毎年、川久保さんが手塩にかけた梅で自家製梅酒を漬けています。
川久保さんはお蚕さまにとても興味をもっていて、6月に春繭を見に来てくれていました。
「次回はぜひ桑刈を手伝いたい!」と、この秋の訪問が実現したのです。

朝見さん夫妻は、6月に川久保さんの呼び掛けに応えて一緒に小高を訪れてくれていました。
お二人ともに熱心にお蚕さまを眺めては、いろいろ質問してくださり「秋もぜひ見たいです」と言ってくれていました。
朝早くの蚕のお食事も、重労働の桑刈も、蚕小屋のお掃除も楽しんでくださったようです。
片道4時間半ほどの小田原は、近い距離ではないなぁと思います。
それでもこうして、蚕という生き物の世話を目的に、小高を訪れる人がたくさんいます。
その力たるや。
ひとを惹きつける力は絶大です。
みんなでひとしごと終えたお昼に、ご褒美がありました。
久米さんのお友だちの愛子さん手作りの「まぜぶかし」。
おいしいんだ、これが!
お料理上手の佐藤宏子さんが作ってくれたミョウガのちりめん塩昆布和えと、愛子さんが育てたかぼちゃの煮物で、オール小高産のぜいたくランチになりました。

5齢の6日目を迎えたお蚕さまの旺盛な食欲も、そろそろ落ち着くころでしょうか。
あしたも5時半起き。
あとひとがんばりです。
(ゆ)
5000分の10
台風に突っ込むように小高から帰宅する道中、生まれて初めて助手席に大好きなひとを乗せていました。
いや、ひとじゃない。
久米さんから「おうちで育ててみたら」と勧められ、10頭の蚕さんを預かってきたのです。
叩きつけるような雨で最速のワイパーも役に立たず、怖い思いをしているドライバーの隣で、選ばれし10頭は静かに振動に身を任せていました。
小高の蚕さんの小田原暮らし2日目、先頭切って1頭が早々と脱皮しました。
写真中央にいる、頭が右を向いている蚕の左横にある、薄い茶色の物体が脱皮後の皮です。

とにかく順調に育っておくれ、と願いながら、帰宅後のわたしは東奔西走しています。
なぜか。
桑がない。
あるのですが、おいしそう、かつもらって良さそうな桑がない。
この時期の桑の葉がゴワゴワとかたいのは仕方ないにしても、道端に、桑がない。
どなたかの畑の中であったり、生えていても葉っぱが散々カミキリムシに喰われたあとだったり。
見つけたのが、海へのトンネルの入り口にある1本でした。
余談ですが、台風後の小田原の海、とてもきれいです。

そんなことより、桑。
そしてもうひとつ心配なのが、蚕さんたちの食欲。
とってもおとなしい。
あんまり食べない。
朝、とりたての柔らかそうな葉をあげたときに初めて3頭同時に桑を食べました。

でも後にも先にも、同時に3頭も食事をしたのはこの時だけ(同居生活が始まって、たったの2日半ですが)。
蚕さんの活発さがない。
なんでなの?
心配で心配で、日に何度も久米さんにメッセージを送ります。
その都度、
「大丈夫」
「食休みじゃない?」
「5齢になるまでの準備期間だから、もう少しゆっくり見てて」
5,000頭のうちの、わずか10頭。
されどこの10頭の蚕のいのち、本当に重みがあるのです。
浮船の里の蚕ベッドに密集している5,000頭を前にしている時は、1頭1頭と向き合うことはありません。
でも自分の目の前にいる10頭は、ひとりひとりの顔が、体が、よく見えるのでもう、大事で大事で。
あすにでも小高へ送り返したい気分ですが、久米さんの言葉を信じて、もう少し待ちます。
そして明日もまた、桑探しに奔走せねば。
こんなに重大な任務を背負わされると思ってもみず、今となっては台風直前に桑刈をしていたときに撮った笑顔の久米さんの写真を、ひとり恨めしく見つめています。(ゆ)

油断大敵
9月19日朝。
昨晩は台風の影響で風が強く吹いていました。
この様子では日の出はとても期待できないであろうと思ったものの5時に目覚しをセット。
カーテンを開けるとどんよりと暗い空が広がっていました。
5時半起床で桑畑に行く予定だったので、出発まで15分ほどだらだらとベッドに横たわっていると。。。
東の空が、ほんのりと薄紅色に染まっていました。
あぁ、油断したな。
たかが朝焼け、されど朝焼け。
美しい空は、今日という一日の始まりを前に気持ちを鼓舞してくれる効用があると思うのです。
朝一番の桑を食べてもらおうと蚕小屋に行くと、昨晩8時にたっぷりあげた桑の葉は

こんな状態になっていました。

小枝もすこぅし太くなった気がします。
さらっと桑の葉をあげただけ、たったの10分くらいの滞在だったのに、やられました。
久米さんのエプロンの胸元に、白く動くモノ。
ふと見た足下と、外履きの甲の部分にも、いました。
油断ならぬ。
どうやってくっついて来たのかしら。
計3頭のお蚕さまがしれっとベッドから抜け出したところを発見され、「こらこら」とベッドへ戻されました。
いったん帰宅し、今日最初の大仕事、おはぎづくりです。
昨日、佐藤さんのおかあさんにいただいた小豆を、久米さんがおいしく煮てくれました。
佐藤さんからはお手製のずんだのあんもいただいて、きれいな二色のおはぎが完成。

手作りって、どうしてこんなにおいしいのでしょう。
小豆のつぶれ具合も甘さも、ちょうどいいあんこで、ぺろりと食べてしまいそう。
おいしく出来たおはぎを佐藤さんご夫妻へのお土産にして、桑畑に繰り出しました。
蒸し暑いなか、最初はどんより曇っていたのに次第に晴れ間が出てきて、雨具を着たわたしたちはじっとりと汗をかくほどに。
すばらしい生育ぶりのためあっという間に欲しい分だけ刈れた桑を浮船号(軽バン)に積み、お蚕さんのところに戻りました。
今度ははっきりと、昨日よりも大きくなったと感じます。
そして、なんか、多くない?
5,000頭と言われて貰ってきましたが、例年の5,000頭よりも明らかに多いような。。
次に会う時はチョークくらいに大きくなっているかしら。
台風から逃げてきたはずなのに、また台風のなかへ帰ります。(ゆ)